進化のイデア 第七章
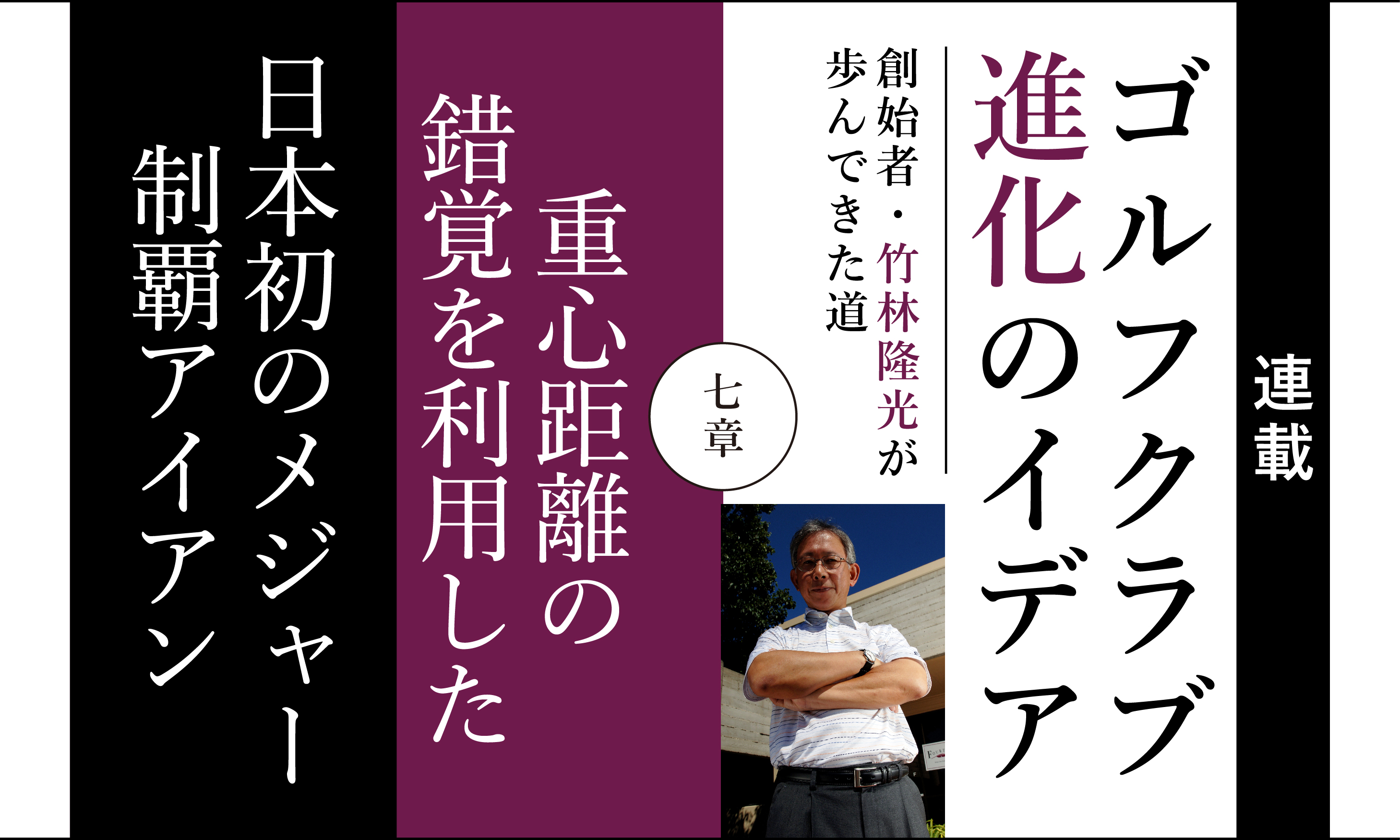
フォーティーンは現代に至るゴルフクラブの進化の礎を作り上げてきたメーカーである。その道を導いてきたのは創始者・竹林隆光。職人の勘に頼っていたクラブ作りに力学を導入し、既存と一線を画したアイデアを形にして、ゴルフクラブを進化させてきたのだ。
記事提供=ゴルフクラシック

七章 重心距離の錯覚を利用した 日本初のメジャー制覇アイアン
アイアンの懐は
設計が決める
ステンレス鋳造アイアンが誕生、浸透してなお、古来ある軟鉄鍛造アイアンの根強い人気は変わらない。帯刀文化を有した日本ならではかもしれないが、確かに鍛冶(かじ)職人がたたき上げた逸品には、あたかも魂が込められているかのような印象さえ抱かぬでもないのだ。
そんな軟鉄鍛造アイアンに、竹林がメスを入れたのは80年代半ばのことだった。その名は『SX‐25』、ヤマハ発のモデルだった。後にそれはスコット・シンプソンの手によって全米オープン制覇の偉業を成し遂げる(87年)。日本製クラブが初めてメジャーVを達成した瞬間だった。が、竹林は特別な何かを施したわけではない。少なくとも一見しただけでは、従来の軟鉄鍛造とどこが異なるか疑問を抱くかもしれない。竹林が変えたのは、根本だった。
「ご存じのように鍛造の歴史は長く、熟練した職人の腕が問われる分野。軟鉄鍛造アイアンもしかりで、経験を積んだベテラン職人が、その勘どころで精度高く仕上げるものでした」。
一方、ステンレス鋳造アイアンで竹林が取った方法は、まず図面を起こし、ネック回りの寸法や重心高さ、重心距離などを綿密に管理。設計値どおりに仕上げるというものだった。明らかに根本が異なる。何よりも竹林には頑とした思いがあった。
「気持いい懐は設計段階で決まる」。
アイアンの構えやすさを大きく左右するネックからフェースにかけてのライン、いわゆる懐。いかにも曖昧(あいまい)な言い方だが、それを解明し、数値で管理することが、いいアイアンには欠かせないと考えていた。
「鍛造メーカーの努力もありました。その頃は以前に比べ、格段に精密に作れるような技術を備えていた。その技術があったからこそ、『SX‐25』も狙いどおりに完成させられることができたのです」。
ハードルとなった
職人のプライド
だが、事は簡単には運ばない。プライド高い、というより、腕に覚えあり、そんな職人の自負が高いハードルとなった。
「当時のやり方としては、金型である程度の形に仕上げ、一定の研磨代を残す。その代を職人の研磨技術で削り、完成品とするのがもっぱらでした。ですが僕が求めたのは、金型でほぼ完成。研磨代は(職人が)なめる程度で十分という考えでした。つまり、職人の技術うんぬんは関係ない。金型の精度こそ重要だったのです」。
見せ所を否定されたのだから面白くない。ただ、竹林は職人の腕を疑ったわけではない。
「今でも鍛造は職人の技量にかかる部分が大きい」と、認めるように職人の技術力は十分理解していた。ただ、すべてを技量や勘だけに頼っていては、そこから先には進めない。
「オレたちはもう何十年もこの方法でやってるんだ」
「そんな金型にしたら持ちが悪いやろ」
そんな言葉が返ってくる。
「時には自分たちが作りやすい金型に変えられてしまうこともありました」。我慢して説得するしかない。竹林もまた負けず劣らず頑固だった。目指したものを作るために、譲ることはなかった。
逃がしながら打てる
プロモデル
寸法や重心位置の管理に加え、『SX‐25』では重心距離の錯覚という手法を試みる。
「その昔、アイアンの重心(スイートスポット)はフェース面の6‐4、ヒール寄りが好ましいとされていました。ネック寄りからインパクトを迎えるため、このようなことが言われたのでしょうが、ハッキリとした根拠は見当たらない。ネック寄りでインパクトするのは、リスクが高く、ゴルファーの心理的圧迫も少なくありません」。
フェースの平面部分の位置にこだわった。
「一般的にフェースサイズと重心距離はイコールと考えられがちですが違います。正しくは、ヘッドサイズと重心距離が比例関係にあります。そこで『SX‐25』では、ヘッドのサイズは通常どおり、フェース面の平坦部分をよりネック寄りに食い込ませ、またヒールへのつながりを滑らかにすることでゴルファーの錯覚を誘いました。構えるとスイートスポット(重心距離)が遠く感じる。しかし、実際に打つとボールがつかまる。そんな仕上がりです」
今で言うやさしいプロモデルといったところか。その昔のマッスルバックは、強度と溶接の問題でホーゼルにはかなりの高さがあった。当然、ネック寄りの重量がかさむため重心距離は短くなる。重心距離30㎜前後も珍しくなかった。なるほどハードだ。瞬時のヘッドターンも確かに利いただろう。だが、逆に言えば、コックを積極的に使って、インパクトでスクエアにできる技術がなければボールは上がらず、距離も出ない。今と違って3I、2Iもフル活用していた時代である。アマチュアのバッグにもほぼ漏れなく3Iがささっていた。どれほど難しいクラブで、難しいゴルフを強いられていたことか。
現在、クラブの条件に、「つかまり」をあげるのがスタンダードとなっている。つかまらないクラブで無理につかまえにいけばミスにつながりやすい。だが、つかまるクラブで、逃がしながら打てれば、精神的プレッシャーははるかに小さくなり、確率高い結果もついてくるのである。
「僕たち(クラブメーカーから依頼を受ける設計メーカー・当時のフォーティーン)は、ハウスメーカーと同じです。注文住宅は数をこなすほど経験や幅が広がります。一つ一つ施主の許可を受けるわけではなく、新しい技術だったり、方法だったり、考え方だったりを、注文を受けた中で試していく。クラブ設計も同じで、依頼を受けた中で新たなものを試す。クラブメーカーにしてみれば、依頼どおりのものが完成すれば問題ありませんし、僕たちもその目的から外れることはなく、新しいことをそっとやってみる。そして、結果がよければ次のクラブにもその技術は生かされていくわけです」。
フォーティーンは年間10機種以上の依頼を受けていた中で、数々のチャレンジを注入した。ただ、それはいたずらに試みていたわけではない。繰り返し行われるテスト結果から得られたものであり、だからこそクラブメーカーの期待を裏切ることもなかったし、メジャー制覇という偉業の貢献もなし得ることができたのだ。