新着記事一覧
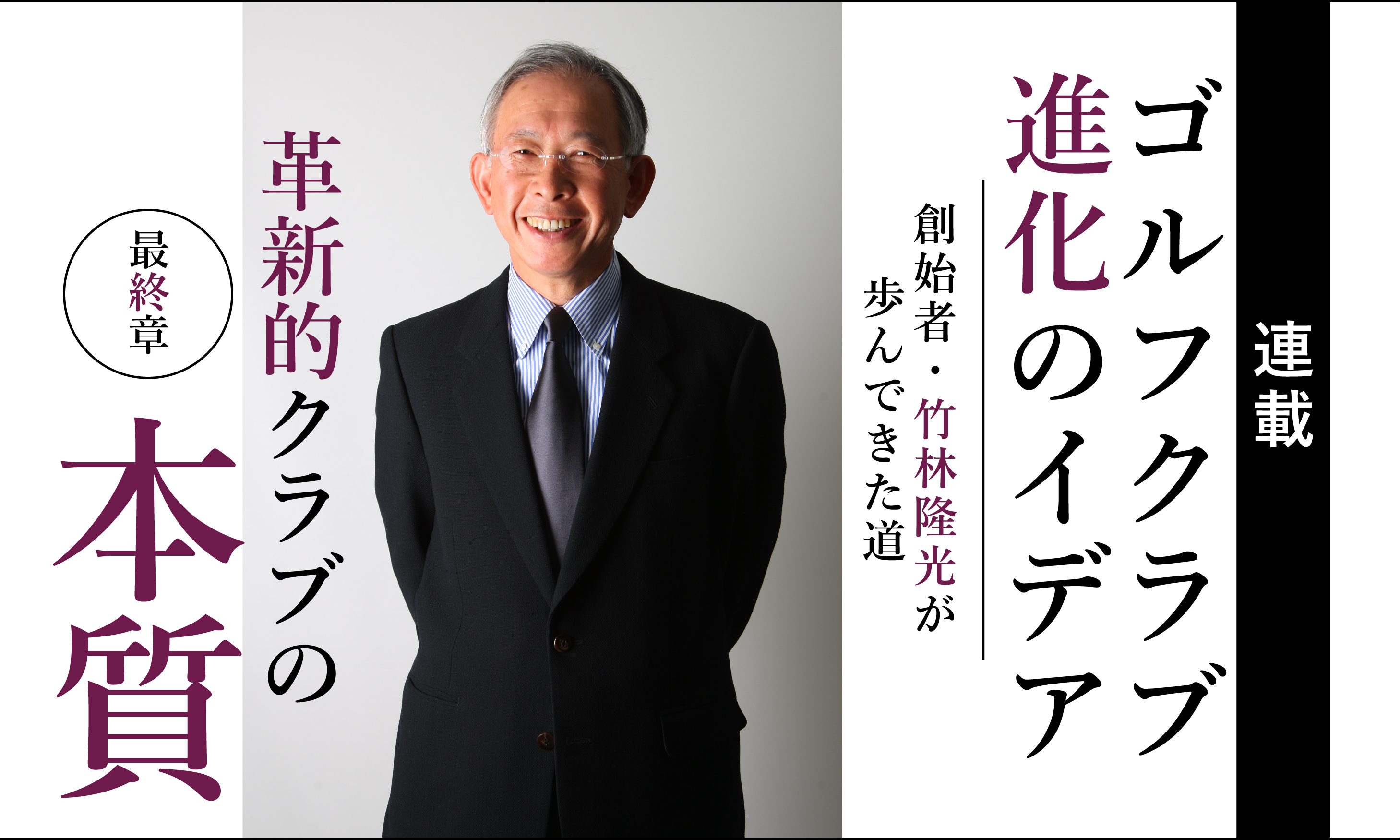
進化のイデア 第十二章(最終章)
「運がよかった。この時代に仕事ができて幸せだった」。 これまでのゴルフ人生、設計家としての道のりを尋ねると、竹林はそう振り返った。 「プロの声を伝え、それを職人が形にする。それ従来のクラブ作りでは当たり前でした。しかし、職人の仕事だったクラブ作りが、徐々に科学(力学)的なものへと変わってきた」。 竹林は「技術革新」と「技術進歩」をあげた。 「まず大きな変化はシャフトがスチールからカーボンになったこと。これで一気に景色が変わりました」。 重量との闘い、それはかつてクラブ作りのうえで避けて通れない道だった。ドライバー一つ取ってもヘッドが200グラム、スチールシャフトは125グラム、グリップ50グラム。トータルすると375グラム。昔の単位にすればちょうど百匁。しかし現在のドライバーは290グラムを切るモデルが当たり前の時代。軽量化はゴルフクラブの進化の根幹そのものなのである。 「次にパーシモンからメタル(ステンレス)、ヘッド素材の変化。シャフト素材、ヘッド素材、両者が変わることなどそれこそ何十年に一度のタイミングでしょう。そこにちょうどいられた、とてもラッキーでした」。 さらには、その後チタン、カーボンへ……。 「重心位置の調整や長尺化などは進歩にすぎません。例えば長尺ですが、その後すべてのモデルが長尺になったなら、それは革新と呼んでいいかもしれませんが、実際はそうではない。対して素材の変化はまさに革新。カーボンにしてもメタル(チタン)にしても、その後、状況は一変しました。ほとんどの人が経験できないことを僕は体験できた。ありがたいことです」。

進化のイデア 第十一章
ここ20年、クラブセッティングは大きく変化を遂げた。ドライバーは460㎤の大型ヘッド、アイアンはストロングロフト化がなされた飛び系アイアン、そしてボールにはロングショット時のロースピン化が施された影響で、ウェッジのセット本数が増えつつある。中でも大きな変化を見せるのは、ショートウッドの充実やユーティリティの浸透によるロング番手でのフレキシビリティだ。プロの世界でも2番アイアンが消え、3番が消え。5番や6番アイアンからのセッティングも決して珍しいものではなくなった。 振り返れば、80年代にプロギアから『インテスト』が登場、タラコの愛称で親しまれ、90年代に入るとキャロウェイが『ヘブンウッド』で、ショートウッドに新たな風を吹き込む。90年代後半には再びプロギアが『ズーム』でユーティリティブームに火をつけ、リョービの『ビガロスメディア』が多くの支持者を集めたのも記憶に残る。 そうした中、別の角度から生まれたのがフォーティーンの『HI-858』だった。 「機能に優れるもののいまひとつ評価されないのが中空アイアンでした。ならば、これが中空アイアンの威力だというものを作りたかった」。 この連載の第三章で触れたように、スタートの思いはそこにあった。 「ウッドからアイアンにかけ形状がリニア(直線的)に変化するクラブを作りたい」。 ゆえに、『HI-858』は単品としてではなく、#2〜SWのアイアンセットとして設計された。が、がぜん評価されたのはロングアイアン。「寝起きでも打てる」、そんな声も聞こえてくるほどで、02年の日本ツアーではユーティリティ部門で使用率1位に輝く。 当初こそプロの反応はまちまちだったという。しかし、ある1打が状況を一変させた。 宮里優作、当時類いまれなるトップアマとして鳴らし、プロトーナメントでも互角に渡り合う力を見せた。そして優勝争いを演じた大会で、アゴの高いクロスバンカーから、ものともせぬ高弾道。 「あのクラブは何だ!」。 プロの間に衝撃が走ったのは01年。そして02年の使用率1位へ。その人気は海外にも飛び火して、同年にはアーニー・エルスの全英オープンVにも貢献した。 「とくにプロ用として考えていた長い番手は全英オープンも想定に入っていました。強風が吹き荒れる全英オープン、風の影響を受けにくいクラブが絶対必要になる」。 まさにドンピシャ、狙いどおりの結果となった。 「あの時は、1発だけでいいから、そういう約束でエルスに渡したんですね。ところが1発打ったとたん、もう1発、もう1発と……。米ツアー会場でのことでしたが、そのまま全英でも使ってくれました」。 若くしてメジャーを制し、一時期遠ざかっていたこともあったのだろう。優勝のインパクトは強烈だった。

進化のイデア 第十章
[[3次元CAD浸透で 表舞台に]] 48インチドライバー『ゲロンディー』でゴルフ業界に一石を投じた竹林だったが、時期ほぼ同じくして2000年を前に、フォーティーンに暗雲が垂れ込める。 「3次元CAD、コンピューターを利用したクラブ設計の浸透です。ウチは比較的早く、95年にはCADを取り入れ、その数年後には金型加工のデータなども含めヘッド工場にCADデータで納品するスタイルを取っていました。ですが、ヘッド工場も次第にCADを採用するようになります。3次元CADを使えば、慣性モーメントや重心位置なども簡単にシミュレーションできます。といってもCADを使いこなす技術は必要ですが・・・」。 早くから取り入れたアドバンテージはもちろんあった。慣性モーメントや重心位置のメリットをいち早く理解し、どういうヘッドが好結果を生み出せるかも掴んでいた。が、数字を打ち込めばある程度の形が見えるため、CADが浸透するにつれ、いつしか似たようなものが多く出回るようになる。そうするとOEMの依頼は、パタッと止まった。 「私たち、フォーティーンは設計会社のノウハウで勝負してきた。だからメーカーとして表舞台に出たくて出たわけではありませんでした。ですが、やらざるを得ない状況だったのです。設計に自信を持ってしていても販売に関しては素人だったので(成功するかどうか)自信はありませんでしたが、もう進むしか答えはなかった。そこで、業界を見渡すと、わりと手をつけられていなかったのがウェッジでした」。 驚異のスピン力でアマチュアも異次元ワールドに導いた『MT‐28』のスタートだった。

進化のイデア 第九章
[[常に長尺の道を 歩んできた]] 90年代後半、竹林は世間をあっと驚かすクラブを送り出す。GET LONGEST DRIVEの頭文字から取った『ゲロンディー』ドライバーがそれだ。何が驚きだったかと言えば、48インチ、その長さにあった。 当時の長さを平均すれば44.5〜45インチといったところ。そこへいきなりの3インチ(7.62㎝)アップ。その名が意図するとおり、「誰よりも遠くへ飛ばしたい」という願いをかなえるドライバーだったが、当初ゴルファーは面食らったような印象もあった。というのも、とかく長尺に対してゴルファーはまゆをひそめる傾向にあるからだ。 ただ、それは織り込み済みのことだった。42.5インチないし43インチの時代に44インチ、44インチ時代には45インチ、常に一歩先の長さを提案してきたフォーティーン。その都度、ネガティブな反応はあったものの、結局クラブもゴルファーも長尺の道を選んできた。フォーティーンは長さが飛ばしに有利なことを確信し、そのスタンスがぶれることは一度としてない。 「正直言えば48インチはやりすぎかな、そう思う部分もありました。ただ、当時は新しい機能を持ったクラブが出てこない時代で、売れない、売れない、皆、口を揃えたようにグチをこぼしていました。そんな閉塞感を打ち破りたかった。私には珍しく“使命感”にかられたんですね(笑)。ですから、よりインパクトある長さにこだわりました」。 90年代序盤から始まった低重心競争が一段落し、新しい方向性が見えてこなかった時代。そんな中での48インチ。振り返れば、“超尺ブーム来る”など、長尺を超え、「超尺」なる言葉も生まれ、雑誌でもいろいろな企画が組まれた。 確かにその飛びは圧倒的で、他メーカーも即座に反応。さらに、片山晋呉や横峯さくらの使用も手伝って、48インチはゴルフ界に新しい風を吹き込んだ。

進化のイデア 第八章
まことしやかに言われる理論の何が正しく、何がまちがっているのか。感覚的にゴルファーが口にする言葉、例えば「粘る」シャフトとはいかなるものを指すのか。その答えを見つけ出すために繰り返してきた数々の実験。一つ一つ確かな道を見い出し、そこに向かって竹林は突き進む。
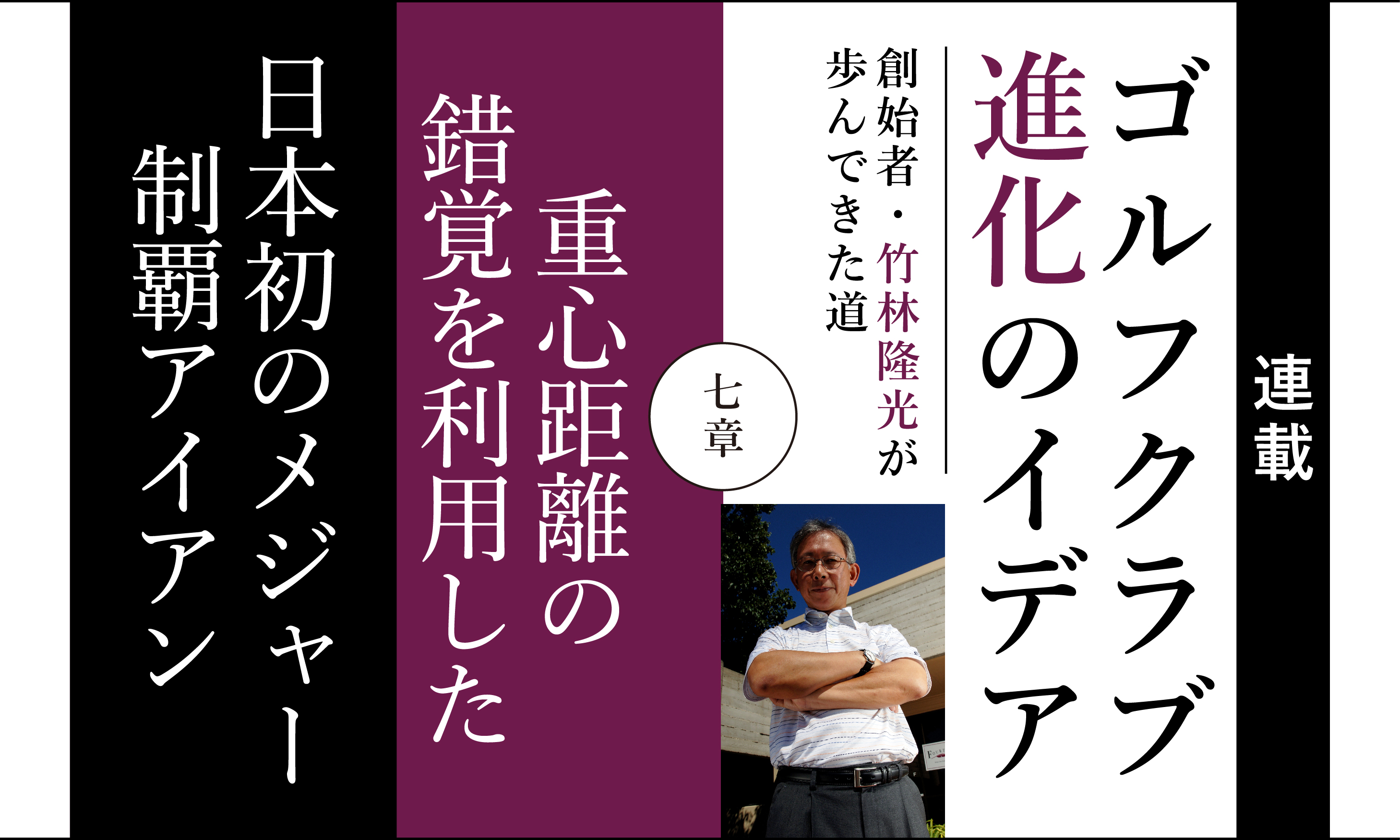
進化のイデア 第七章
[[アイアンの懐は 設計が決める]] ステンレス鋳造アイアンが誕生、浸透してなお、古来ある軟鉄鍛造アイアンの根強い人気は変わらない。帯刀文化を有した日本ならではかもしれないが、確かに鍛冶(かじ)職人がたたき上げた逸品には、あたかも魂が込められているかのような印象さえ抱かぬでもないのだ。 そんな軟鉄鍛造アイアンに、竹林がメスを入れたのは80年代半ばのことだった。その名は『SX‐25』、ヤマハ発のモデルだった。後にそれはスコット・シンプソンの手によって全米オープン制覇の偉業を成し遂げる(87年)。日本製クラブが初めてメジャーVを達成した瞬間だった。が、竹林は特別な何かを施したわけではない。少なくとも一見しただけでは、従来の軟鉄鍛造とどこが異なるか疑問を抱くかもしれない。竹林が変えたのは、根本だった。 「ご存じのように鍛造の歴史は長く、熟練した職人の腕が問われる分野。軟鉄鍛造アイアンもしかりで、経験を積んだベテラン職人が、その勘どころで精度高く仕上げるものでした」。 一方、ステンレス鋳造アイアンで竹林が取った方法は、まず図面を起こし、ネック回りの寸法や重心高さ、重心距離などを綿密に管理。設計値どおりに仕上げるというものだった。明らかに根本が異なる。何よりも竹林には頑とした思いがあった。 「気持いい懐は設計段階で決まる」。 アイアンの構えやすさを大きく左右するネックからフェースにかけてのライン、いわゆる懐。いかにも曖昧(あいまい)な言い方だが、それを解明し、数値で管理することが、いいアイアンには欠かせないと考えていた。 「鍛造メーカーの努力もありました。その頃は以前に比べ、格段に精密に作れるような技術を備えていた。その技術があったからこそ、『SX‐25』も狙いどおりに完成させられることができたのです」。

進化のイデア 第六章
[[トゥシャフトは サードゴロ]] フォーティーン本社、今はショールームとなった部屋には、かつてパーシモンが所狭しと並んでいた。そして片隅には妙なクラブもいくつか立てかけられていた。例えばウッドのクラウンの中央部分が円柱状にくりぬかれたもの(クラウンからソールまで円が貫通した状態)。あるいは、あらぬところからシャフトが飛び出しているクラブもある。「妙な」という表現、決して的外れではない。その数々が、既存を疑わない竹林のスタンスの表れ、実験で得る糧だった。 「いろいろやりましたね。例えばアイアンのヘッドを切断してトゥ側に付けたり、あるいはネックを切って位置をずらして溶接したり。前者は重心距離、後者はグースの違いでどんな結果になるか、試しました。今はロストワックスで簡単に作れますが、当時はとても大変な作業でした」。 またウッドでは重心距離ゼロ、つまりヘッドの重心がシャフトの真下にくるようなクラブを試したこともあったと言う。さて、右に出るか、左に出るか。結果はいつも神のみが知る。 「そもそもスイング中にフェースの向きがまったくわかりませんでした。しかも慣性モーメントが小さくなるからボールは右にも左にも出るし、距離はまったく出ない。『クラブってよくできているな』、このテストで実感したのがこれでした(笑)」 続けてトゥ側にシャフトを付けたヘッドも作ってみたが……。 「マイナスの重心距離ですね。これは野球で言えばサードゴロみたいなボールばかりでした」。

進化のイデア 第五章
[[十年来のファンを 無視してでも]] フォーティーンとしてプロギア『500シリーズ』のOEM設計を成功に収めると、竹林に対する周囲の評価も次第に変わってきた。 「数字でクラブの何がわかる?」「いいクラブはいい職人が作るものだ」 設計値や理論が前面に押し出される昨今、にわかには信じ難いが、当時はそれがあたりまえ。新しい風を吹き込もうとする竹林の耳に聞こえてくるのも、そんな非難の声ばかりだった。だから、『500シリーズ』の成功にまゆをひそめた向きもいたことだろう。何よりも伝統を重んじる競技、少なくとも手放しで大歓迎という空気ではなかった。 が、しばらくすると今度は海外ブランド、パワービルトから依頼が届く。パワービルトと言えば、かつて青木功やジャンボ尾崎も愛用したほどのゴルファーブランド。日本では不動産や観光、運輸事業などを展開する一大企業、国際興業が取り扱い(当時)、依頼も同社からのものだった。ただし、『サイテーション』で一世を風靡した頃に比べ、その勢いは減速し始めていた。 「設計依頼の話があり、担当者からいきなり、取引するにあたってまず重役に会ってほしいと。面接ではないですが、雰囲気としてはそんな感じで、“大学入学の直前、父が買ってくれた最初のクラブがパワービルトでした”、そんな受け答えをしたのを覚えています(笑)」 “面接”はすんなりと済んだものの、設計依頼の内容はのめるものではなかった。 「十年来のパワービルトファンがいる。そうしたファンを裏切らないモデルを作ってほしい」 すなわち、従来の伝統は崩さないでくれ。 「伝統にとらわれたクラブ作りこそファンが離れた要因、そう思っていたから反対しました。あえて『Power Bilt』の刻印を外すことを提案しました」 完成したその名は『モメンタム』アイアン。確かにあらためて確認すると「Power Bilt」の刻印はそこになかった。

進化のイデア 第四章
[[同じ考えを持った メーカーが出現]] 81年、晴れて竹林は独立、群馬にゴルフクラブ工房フォーティーン(当初は藤岡、その後現在の高崎へ)を設立する。主に設計委託中心のスタートだったが、早くも大資本、なんと横浜ゴム(プロギア)から依頼が入る。 プロギアがスポーツ事業分野に本格参入したのは83年。同年には、既存品とは異なるヘッドスピード別設計ボールを発表。その第2弾として、同じくヘッドスピード別に設計したクラブ(アイアン)、それが竹林に出されたリクエストだった。 「ゴルファー別にクラブを作る、それは私たちがずっとやってきたことだったので、やっと自分たちと同じ考えをもつ会社が現れた、そんな思いを抱いたものです」 手掛けたモデルは『500シリーズ』(3機種)。「三兄弟」とアピールされた中空アイアンだった。 「ヘッドスピード別に、理想的な重心距離、重心深度、重心高に設計したクラブです。重心距離や重心深度に関して言えば、ヘッドの慣性モーメントで考えればもっと分かりやすかったのでしょうが、当時はその概念がなく重心距離、重心深度、それぞれの視点から設計。ただし全番手が中空というわけではなく、例えばハイヘッドスピーダー用はロングアイアンだけ、ローヘッドスピーダー用はミドルアイアンまでと、ヘッドスピードに応じた中空構造を採用しました」。 発想も技術も、当時は群を抜いていた。『500シリーズ』には、新機軸から当時のタブーまで、その数々が詰まっており、クラブ作りの大きな分岐点となったモデルになった。

進化のイデア 第三章
竹林がクラブを研究すること、それは既存の理論を疑うことが全てだったと言える。 「例えばパーシモンの頃は、重心が低いからボールが上がりやすい。こんなことが当然のように語られていたものです。ところが実験してみると明らかに事実に反していた。ティアップして打つドライバーは、低重心ヘッドにすることでボールのバックスピン量が抑えられ、決して上がりやすくなるわけではありません。当時は、誤った解釈ばかりがゴルフクラブの定説とされていました」。 一つの理論があれば、果たしてそれが真実か、まずは疑う。その理論が真か否かを判断するために、竹林はゴルファーの視点でクラブの力学を研究し続けたのだ。 現在のようにクラブ設計がコンピューター化された時代なら、力学的根拠を導き出すことは簡単なことだったかもしれない。数値を入れてシミュレーションしてみれば明確な答えがはじき出される。だが、当時はもっぱらトライ&エラー。試作しては試し、試しては試作の繰り返し。気の遠くなるような作業だったが、むしろそれは竹林にとっては“やり甲斐”でしかなかったのだ

進化のイデア 第二章
[[本質を楽しめる クラブを作るために]] スライス病に竹林が陥ったのは大学1年、秋のことだった。その翌年、大学2年時には早くもゴルフクラブを作る仕事に就こうと決心。その意志は曲がることなく、卒業と同時にクラブメーカーに就職した。 その一方で競技ゴルフはやめなかった。大学ゴルフ部出身でクラブメーカーに就職すると、「プロになれなかったからだろ」と思われがちだが、それは本意ではなかった。竹林には競技ゴルファーとしての意地があったのだ。 「競技ゴルフも嫌いではありませんでしたが、それ以上に自分でチューンナップしたクラブで競技をプレーしてみたかった。クラブによる違いを実戦で感じることに興味が移っていったのです」。 スコアだけを競うのではなく、知らなかった世界にクラブの力で到達できるか。ゴルフというゲームの本質が楽しめるようなクラブを作りたいという思いは、日増しに強くなるばかりだった。

進化のイデア 序章
[[芽生えた 不審の心]] なぜ止まっているボールをうまく打てないのか。 プレーを始めたころ、多くのゴルファーが味わう思いを竹林隆光もまた感じた。高校まで野球に打ち込み、大学入学と同時に好きで選んだゴルフ部。もちろん竹林も練習に余念はなかった。だが一方で、「道具の影響力のなんと強い競技だろう」という思いを即座に抱くようになった。 今でこそクラブの種類はじつに豊富だが、竹林がゴルフを始めた60年代後半はパーシモンウッドに軟鉄鍛造アイアン全盛。もちろんクラブメーカーも複数ありはしたが、それらに大きな違いはさほどなかった。今あるクラブでうまく打てるようになる、それが当たり前の時代だった。ところが竹林はクラブそのものを疑う心が芽生え、次第に高まっていったのだ。